| 【第11回】 《第3章 大阪コレクションの光と陰-続》 |
| ■低い知名度と秋1回の変則開催 |
| 1987年、鳴り物入りでスタートした「大阪コレクション」だった。スタートから3年ほど経って、大阪府・市および財界の事実上の認知を得たこのプロジェクトは、当然、順風満帆に走り出すはずだった。いや、少なくとも形の上では、そのように見えていたかもしれない。だがその実態は、決して順風とは言えなかった。外から見た目には気付かなかったかも知れない。だが、我々自身の気持ちの中では、「将来は、世界5大コレクションに肩を並べるコレクションに」の掛け声が、3〜4年目になると、ややむなしく感じられるようになっていた。 |
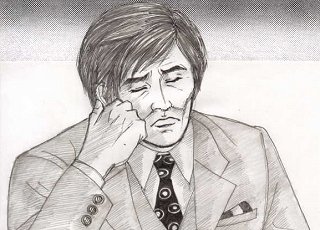 (イラスト: Yurie Okada, ROGO Ltd.) |
| 第1は、やはり知名度不足で、看板のコシノヒロコさんだけでは如何ともしがたかった。もともと大阪におけるファッションデザイナーは量的に少なく、知名度も低かった。その現実を踏まえた上での「大阪コレクション」の旗揚げだったのだから、それも当然といえば当然だった。このため、東京で活動している関西ゆかりのデザイナーを口説き落とし、箔付けを狙ったが、それではどうしても「東京コレクションの二番煎じ」の感を免れなかった。こうして大阪コレクションは、スタートから3〜4年を経ても、なおファッション界においては「ローカル・イベント」の域を出なかった。 第2は、世界の有力コレクションが、いずれも春・秋2回開催され、デザイナーたちはその2回のコレクションで「秋冬もの」と「春夏もの」の計4シーズンの作品を発表する。だから、そこにバイヤーたちも大勢集まり、商談も成立する。だが大阪コレクションは年1回、11月、それも東京コレクションが終わってからの開催になり、しかもメインのコシノさんたちの作品は先に東京で発表されるとなると、ファッションの専門家にしてみれば、あえて大阪コレクションを見る必要がなかった。それはプレスの反応も同じだった。 1回、2回は主催者側にも勢いがあった。「継続は力なり」を信じ、とにかく突っ走るだけだった。しかし、1989年の第3回目のとき、同時に開催されたワールド・ファッションフェア(WFF)を見て、その差の大きさに愕然とさせられる。そして、大阪コレクションの仲間の多くが、「今のままの運営を続けていては、いずれこの事業は消えてしまう」との危機感を抱くようになっていた。 |
| ■新人デザイナーにチャンスを |
| 第5回開催のための選考委員会が開かれたのは1991年6月だった。顧みると、日本経済が絶頂を究めた最終局面に入った時期だった。新規に出品を希望するデザイナーも増え、結果的に15年の大阪コレクションの歴史の中で、最多のステージ数(12ステージ)を数える。低調だった第4回を5ステージも上回り、運営サイドの我々としては大いに意気が上がる。実際、コシノ3姉妹の母親である小篠綾子さんの特別参加もあり非常に盛り上がったコレクションが開催される。 |
 (初期の頃の新人ジョイントステージ) |
| だが選考委員会の席上、デザイナーの委員を中心に反省と新たな提案が出される。そして、そのリーダー格のコシノヒロコさんから次のような要望がでる。 「今年は、これまでで最も多いデザイナーが参加してくれそうだが、メンバーが固定してしまい、先々を考えると、その数が飛躍的に増える可能性はない。参加資格の条件を再検討し、もっと若いデザイナーが出品できるようなことを考えてもらいたい」 もっとも、大阪コレクションへの参加資格は当然ながらデザイナーの皆さんで考えてもらったもので、われわれの都合を押しつけたものではない。むしろ、厳しい条件を出し、それでも大阪コレクションに挑戦しようという意欲あるデザイナーを選ぼう、というのが参加資格を決めた前提にあった。だが、残念ながら関西で活躍しているデザイナーにとっては、やや厳しすぎる条件であったようである。しかもこの時代、DC(デザイナーズ・キャラクター・ブランド)ブームが起こっており、名もない若いデザイナーたちが巷に育ち出している頃だった。コシノさんたちの提案は、こうした若いデザイナーにチャンスを与える場を作ってほしいというものだった。 もちろん、当初の参加資格もデザイナーの皆さんで作ってもらった参加資格は(1)出品料300万円の負担ができる(2)1ステージで100体の作品を出品できること(3)その上で、選考委員会の推薦を得ること――となっていた。この参加条件を維持しつつ、新人の若いデザイナーに関しては、出品料は無料、ただし5名以上で1ステージを構成する、というのが具体的な提案だった。 その提案をのむことは、運営サイドに立ってみれば大きな費用増につながる。またわれわれとしては、当時、コシノさん以外のデザイナーは基本的に若いデザイナーとの認識があり、「若いデザイナーの発掘・育成」という課題には対応しているとの思いがあった。しかし、さらにその裾野を広げてほしいというデザイナーの皆さんの提案にも一理があり、結果としてこのコシノ提案を受け入れることにした。こうして新設されたのが、現在では大阪コレクションの売り物となっている「新人ステージ」であった。 |
 (初期の頃の新人ジョイントステージ) |
| 実際に事務局を担当している私としては、多少の心配もあった。この年は、出品デザイナーが過去最多の12名になり、取り分け3姉妹の母親、小篠綾子さんには人気爆発の予感があり(実際にそうだった)、採算的にも十分勝算があった。しかし、このような状態がいつまでも続く保証はない。 内心、大きな不安を抱く私だったが、相談した実行委員長の能村龍太郎太陽工業会長は「面白い、やってごらんなさい。赤字が出てもそれ程にはならないでしょう。その程度はわれわれで何とかなるでしょう」とゴーサインを出す。そうなると、こちらも大船に乗ったのも同じ、コシノさんたちに了解した旨を伝え、即座に「新人ステージ参加デザイナー」の募集活動に入る。 もっとも「赤字が出ても知れているだろう、その程度は何とでもする」といってくれた能村さんは、その口も渇かぬ間に、「折目さん、事業というものは、1円といえども赤字を出してはいけない。1円でも良いから黒字を出し、それを蓄積する。それが事業の要諦です」と、おっしゃる。事業の原則と、人使いの妙を学んだ私だった。 また、スケジュールぎりぎりで、無理を承知で、思いも掛けない提案をさりげなくわれわれにしてくるコシノさんの、ぎりぎりまで、よいものを作るために妥協を許さないクリエーター魂からも学ぶものがあった。 |
| ■応募者の地域・国籍を問わず |
| こうして1991年11月の第5回「大阪コレクション」から、「新人ステージ」が新設され、以後今日まで継続されるとともに、このステージから続々と有望な若手が飛び出し、「大阪コレクションの柱の事業」と評されるほどに育っていくのである。 この年は、実験の意味もあり、18名の若手が3ステージに分かれて出品したが、以後、1ステージ5〜6名が参加、これまでに、都合64名(組)の若手デザイナーがこのステージから巣立っていった。そして今年の11月にも5名が新たに加わる。 この新人ステージにも、一応の参加条件はある。だがそれは、「独立して1年以上の活動実績があること」の1点で年齢、地域、国籍など全く問わない。だから、「大阪コレクションだから、大阪や関西のデザイナーを優先する」ということも全く無い。最近ではインターネットに乗せて海外にも、「大阪に来たら、出品料無料で作品を発表する機会があるよ」と参加を呼び掛けている。 |
 (ロシア人 ミハイル パンチレエフさんの作品) |
| このため、パリやニューヨークなど海外で修行中の若手からの応募がかなりあり、現実に数組が選考され、このステージを踏んでいる。そのニューヨークからの1人は、ベトナム人デザイナーをパートナーとしての参加となった。また、日本人の介在者がいたとはいえ、モスクワから応募した若手も2人選考されている。さらに昨年はソウルから、今年も東京を活動拠点にしているがブラジルの日系3世の参加が決まっている。やや自嘲気味ながら、大阪で開催される事業としてはなかなか国際的である。 |
| ■世界に飛び出す若手も輩出 |
| 64名(組)の若手の中には、その後著しい活躍をするデザイナーも続出した。第5回、つまり新人ステージの1期生となる山下隆生は、大学で建築を学んでいたが、親の反対を押し切りファッションに転じた変わり種である。作品自体も評価されたが、その後の活動も積極的だった。そして3年後には、一気にパリに進出、パリ・コレクション期間に併せてゲリラ的にショーを行う。通常、大阪で多少成功すると、次の舞台は東京となるが、彼の頭にはそれはなかった。どこかでショーができるならどこでもいい。たまたまそれが、ファッションの都パリであった、という感覚だった。 最初のパリでの挑戦は大成功だった。パリのファッション専門紙は、わが国の第一人者の一人川久保玲さん(コムデギャルソン)と並べて、山下の作品を紹介した。東京を経ずして一躍、山下はヤングファッションの旗手に躍り出た。 |
  (山下隆生さんと、20471120のステージ) |
| 「20471120」という数字を並べたブランドを持つ中川正博&Licaは2期生だが、彼等もすぐに山下を追いかけた。洋画を学ぶ中川とファッションを専攻したLicaがチームを組んだメゾンだが、彼等も瞬く間にカリスマデザイナーの仲間入りを果たす。その作品も面白いが、それ以上に愉快なのは、次々にファッションショーの常識を覆していったことだ。閉鎖したゴルフ練習場を借り切ったり、夜の公園を会場にしたり、さらには木下サーカスに乗り込み、競演を提案、それを実現させたこともあった。また土砂降りのヘリポートで、大粒の雨に打たれながら感動的なショーをやり切ったこともある。 3年前、週刊朝日が「21世紀の日本のファッションデザイナー」をグラビアで紹介したことがある。その3組の中に山下隆生と中川正博&Licaが選ばれていた。 この2組人に続く若手も続々誕生している。いずれ彼等を紹介することもあるだろう。言えることは、強い先行き不安から創出された「新人ステージ」が、われわれの理解を越えてファッション界に知られるようになり、逆に「あのような若手を輩出させる大阪コレクションとは何?」といわれ出したのもその頃からである。 |
| (文中の敬称はいずれも当時) |
| 『千里眼』No.76(2001年12月25日)掲載 |
|
|